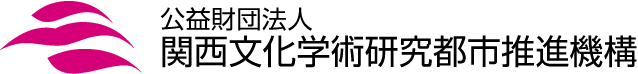2月1日(木)13:30から、大阪科学技術センター(大阪市西区)の会議室を会場に、先端シーズフォーラムを開催しました。
当日は、強力な寒気団の接近により、夕方からの降雪が全国的に強まる可能性が天気予報で報じられる中、63人が参加されました。
主催:(公財)関西文化学術研究都市推進機構
共催:(公社)関西経済連合会
後援:(公大)京都府立大学、(公財)地球環境産業技術研究機構、(一財)大阪科学技術センター)
 主催者挨拶
主催者挨拶
関西文化学術研究都市推進機構 常務理事・事務局長 中川雅永
- 講演1「木材利用の未来を切り拓くイオン液体を用いたバイオリファイナリー技術」
京都府立大学大学院生命環境学研究科 教授
産学連携リエゾンオフィス副所長 宮藤 久士 氏 木材を溶かせる特殊なイオン液体により木材の成分を分離。セルロースからグルコースへの変換を経て、燃料や合成樹脂原料になる5ヒドロキシメチルフルフラート(5HMF)を、一つの反応系(ワン・ポット)で取り出せる。また、触媒を用いず、比較的低温で安全に反応が進み、装置の簡便性も見込めるなどのイオン液体の特質を活かして、従来の有機溶媒では難しい、5HMFを効率よく回収する減圧水蒸気蒸留という極めて特徴的な技術を開発中。別の木材成分リグニンからはバニリンに変換できる。
木材を溶かせる特殊なイオン液体により木材の成分を分離。セルロースからグルコースへの変換を経て、燃料や合成樹脂原料になる5ヒドロキシメチルフルフラート(5HMF)を、一つの反応系(ワン・ポット)で取り出せる。また、触媒を用いず、比較的低温で安全に反応が進み、装置の簡便性も見込めるなどのイオン液体の特質を活かして、従来の有機溶媒では難しい、5HMFを効率よく回収する減圧水蒸気蒸留という極めて特徴的な技術を開発中。別の木材成分リグニンからはバニリンに変換できる。 - 講演2「炭素循環社会の実現を目指したバイオ燃料・グリーン化学品生産」
地球環境産業技術研究機構バイオ研究グループ リーダー・主席研究員 乾 将行氏

「RITEバイオプロセス」は、バイオマス由来の糖類を、遺伝子組換えしたコリネ型細菌を増殖させることなく、化学触媒のような使い方をして、微生物が持つ物質変換機能を活かして効率よくバイオ燃料やグリーン化学品を生産する、RITE のコア技術。
RITEバイオプロセスにより、バイオマスからジェット燃料や水素、バイオプラスチック、医薬・化粧品・香料等の原料となる芳香族化合物等を製造。機能を高めた微生物を短期にデザイン、実用化する「スマートセル」プロジェクトにも参加し、さらに難易度の高い芳香族化合物の生産技術の開発にも取り組み中。 - プレゼンテーション1「未開の国産資源「リグニン」で創る新産業」
森林研究・整備機構 森林総合研究所 新素材研究所長
研究コンソーシアム SIPリグニン研究代表 山田 竜彦 氏 木材の成分のうち、リグニンに着目して研究・開発。リグニンは、一種類の化合物ではなく、多様性を併せ持つ。工業化に向けて、日本に最も多くリグニンの多様性が非常に少ない"杉材"に樹種を絞り、ポリエチレングルコールを使い硬化可塑効果を応用した物性制御技術で改質したリグニンを用いて、エンジニアリングプラスチック相当のマトリックス樹脂を製造するベンチプラントを操業し、製品には電子基板やクルマの部材、3Dプリンターの基材樹脂も。バイオマスの原料は、国内製材工場の端材利用などにより、経済性も高まる。国産資源として「海にはメタンハイドレート、山にはリグニンが眠っている」と考えている。
木材の成分のうち、リグニンに着目して研究・開発。リグニンは、一種類の化合物ではなく、多様性を併せ持つ。工業化に向けて、日本に最も多くリグニンの多様性が非常に少ない"杉材"に樹種を絞り、ポリエチレングルコールを使い硬化可塑効果を応用した物性制御技術で改質したリグニンを用いて、エンジニアリングプラスチック相当のマトリックス樹脂を製造するベンチプラントを操業し、製品には電子基板やクルマの部材、3Dプリンターの基材樹脂も。バイオマスの原料は、国内製材工場の端材利用などにより、経済性も高まる。国産資源として「海にはメタンハイドレート、山にはリグニンが眠っている」と考えている。 - プレゼンテーション2「最近のイオン液体 開発動向と市場性」
日本乳化剤株式会社 研究開発本部企画開発部 担当部長 堀 哲也 氏

イオン液体を実用化したい観点で弊社は取組み中。イオン液体で重要な点は、構造デザインが可能な点。当社はカチオンとアニオンの組み合わせを特に重要視し、市場化を模索。「値段が高くなる」「化学物質登録も必要」「安全性を担保」を踏まえて、市場が求める設計をすることが、イオン液体の市場性を考える際に重要。
バイオマスでは、「有用な成分を溶かして取り出す」「溶けたものを分解して各成分を取り出す」の2つが重要。前者はリン酸系のイオン液体が良い傾向。後者は、クロライド系など、酸性サイドのものが分解する傾向がある。ビジネスを見据えて、セルロースに様々な反応基を付けて、実質的にセルロース改質して溶剤に溶解して使うなど、様々な研究が行われ、少しずつ動きがある。繊維を作る分野も、多少は動きがある。バイオリファイナリー関係において、ビジネスとして成立するにはイオン液体のリサイクルが重要。安全性や化審法の登録についても、十分に注意を払う必要がある。
パネリストお二人からの自己紹介を兼ねたプレゼンテーションに続き、あらかじめ会場参加者に配布した質問アンケートへの回答を通じて議論に参加できる形で、「バイオマス利用の現状と課題、そして進む方向」と題して、パネルディスカッションが行われました。
- パネルディスカッション「バイオマス利用の現状と課題、そして進む方向」